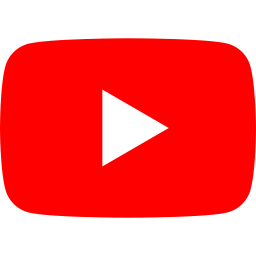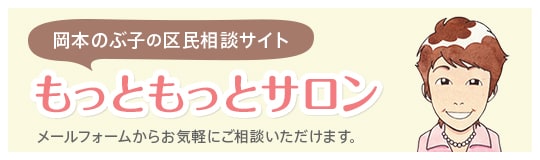決算特別委員会(区民生活所管)10/3
本日、2025年10月3日 決算特別委員会の区民生活所管に公明党区議団より、河村みどり議員と岡本のぶ子の2名で登壇させて頂きました。
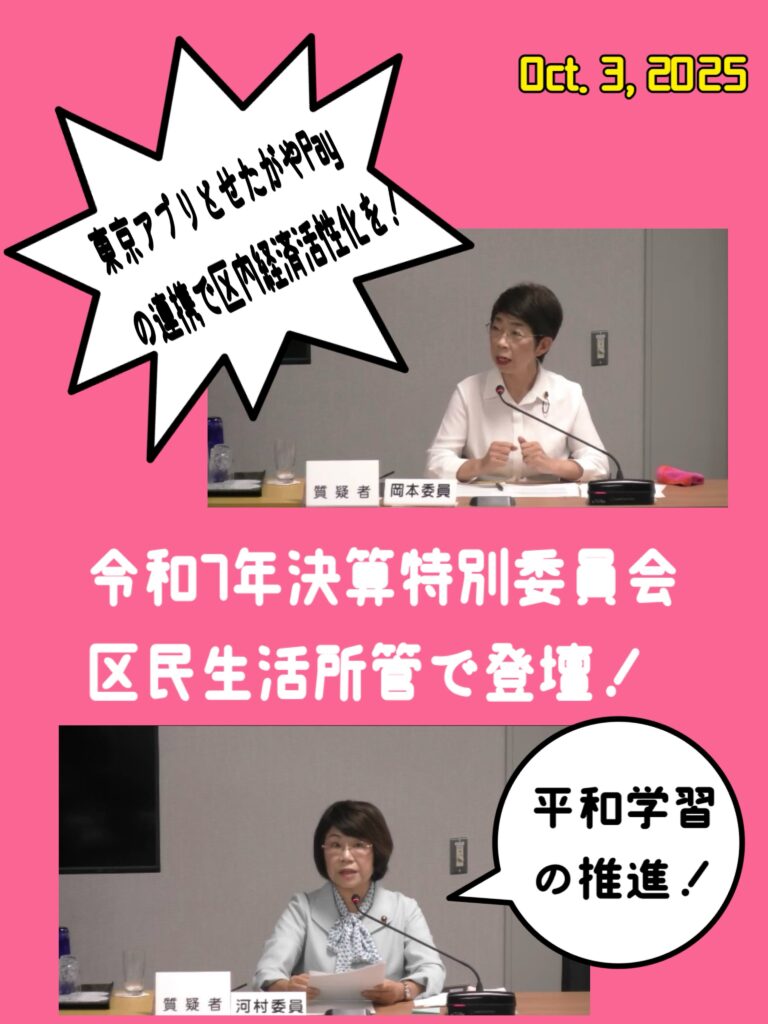
岡本のぶ子の質問と答弁を要約してご報告させて頂きます。
(1)まちづくりセンターの「オンライン相談」について
質問:令和6年10月から全28地区で本格実施がスタートしたオンライン相談の実績が、今年の8月までに6件。余りに少ない。ニーズに応えているのか疑問。区民へ情報を届ける工夫と共に、まちづくりセンターの「オンライン相談」で、申請等の手続きが完結できるよう機能の充実を求める。
答弁:「福祉の相談窓口」において、接続先である担当所管等と連携して、オンライン申請を行うことができるよう相談者に寄り添ったサポートを丁寧に実施してまいります。

(2)「おくやみコーナー」の設置について
質問:2023年の区民の死亡者数は7679人。ご遺族等の行政窓口での諸手続きをサポートする「おくやみコーナー」の本格設置が待たれている。モデル実施を踏まえて「おくやみコーナー」の常設化&ワンストップ化を求める。
答弁:委員のお話のワンストップでのおくやみコーナーも含め、今後、庁内関係所管殿調整や必要な手続きを進め、令和8年度中の常設のおくやみコーナーの設置を目指し取り組みを進める。

(3)東京アプリの連携先にせたがやPayを活用した区内産業の活性化について
質問①:本年6月第2回定例会での代表質問で東京アプリとせたがやPayの連携の準備を求めた。その進捗を伺う。
答弁①:令和8年度予算を精査する材料として、東京都より技術仕様書の提供を頂き、実施主体の商店街振興組合連合会、システム開発・運用を担うベンダーにも当該技術仕様書を共有し、ポイント連携に必要な経費の見積を依頼している。今後、当該見積を基に、関係者間で令和8年度のポイント連携に関する調整を図っていく。
質問②:令和7年4月8日時点の本区の15歳以上のマイナンバーカード保有者数は597,197人。仮に、全ての方が、東京アプリをダウンロードし、マイナンバーカードで認証を行った場合、7000P/人・合計41億8千37万9千円分のポイントが東京都から付与されることになる。仮に、せたがやPayのアクティブユーザー10万人の区民&都民が、せたPayを連携先に選んだ場合、区内商店で7億円の消費が期待できる。経済的インパクトについて、区の認識を伺う。
答弁②:あくまでも仮定に基づくことだが、委員からお話のあった東京ポイントとの連携により生じ得る7億円と言う規模は、区内産業にとって大きな経済的インパクトが期待できるものと考える。
質問③:東京アプリの仕様に合わせて、せたがやPayの利用対象年齢を現在の16歳以上から15歳以上に引き下げることが必要。
答弁③:商店街振興組合連合会内部でのコンセンサスや、資金決済法に基づく変更の届出等、必要な手続きを整理の上、年齢制限の引き下げについて検討を開始する。
質問④:東京アプリのポイントの連携先として「せたがやPay」を選んで頂くために、他の媒体に負けないインセンティブが必要。例えば「せたがやPayポイント1000ポイント上乗せ」など、お得感が出るキャンペーンが有効と考える。
答弁④:必要に応じて、東京アプリと連動したポイントの上乗せといったインセンティブを設計するなど、せたがやPayへの誘引を促し、区内経済の発展に資する効果的な施策の立案を検討していく。

(4)大規模災害時の指定避難所の運営について
質問①:令和6年第2回定例会一般的質問で、ペットの同行避難訓練の実施が着実且つ計画的に進むよう、区が責任を持って取り組むことを求めた。まず、東京都獣医師会世田谷支部の先生方のご協力を頂き、まちづくりセンター防災担当職員への令和6年度の研修会の実施状況を伺う。
答弁①:ペット同行避難については、地域防災計画(令和7年修正)において、修正の重点検討項目として取り組んでいる。令和6年度は、獣医師会に講師を依頼し5支所で職員向け勉強会を実施し、合計で82名受講した。
質問②令和7年度以降も継続して、未受講者への研修の機会が必要。
答弁②:今年度は、新規採用職員と横転者向けに全支所合同の勉強会を実施できるよう進めていく。また、来年度以降も効果的に知識習得につながる取り組みを検討しいていく。
質問③:指定避難所のトイレ対策として、水洗トイレが使用不可の場合、トイレ個室の便座を活用した簡易トイレの使用が考えられる。簡易トイレの設置及び利用の留意点など個室トイレ内にパネルなどで貼り出す必要がある。区として備えがあるか?
答弁③:区の作成した避難所運営マニュアル標準版には、トイレの準備の手順の記載はあるが、個室内の簡易トイレの使用方法などについての手順についてパネルなどは、現在ない。
今後は、専門家の意見も参考に、わかりやすいトイレの使用手順などの導入について検討する。
質問④:指定避難所内での性被害防止に向け、特にトイレ利用の男性、女性、子供の導線への気配りや夜間や停電時の照明器具の備えが必要だ。区の備えを伺う。
答弁④:災害時に停電した場合の避難所における照明手段として、発電機と合わせて、投光器、LEDランタン、懐中電灯などが備えられていて、運用は避難所運営委員会に一任されている。性被害防止に向けては、レイアウトの工夫や犯罪が起きにくい環境づくりについて運営マニュアルに記載もあることから、その点も避難所運営委員会や訓練などで確認していく。
質問⑤:ペット同行避難の受け入れ訓練や、トイレ対策など、円滑且つ適切に進めるためには、避難所運営を担われる方や地域住民の理解が深まることで、自発的な取り組みが進められると考える。
そのために、希望される指定避難所単位での講習会の実施など学習機会の充実が必要。
答弁⑤避難所運営委員会などでの災害時のトイレやペットなどの情報提供をすると共に、身近な
まちづくり推進協議会や防災塾などの様々な機会を捉えて、周知啓発を重ね、自発的な取り組みが増えていくように支援していく。

(5)地区発の文化•芸術の交流を支える公共の役割について
質問①:桜丘地区は「音楽を通じてのまちづくり」を掲げ、約30年間にわたり、桜丘ホールで様々な音楽会が開催されている。ピアノの劣化が著しく更新が必要。
答弁①:新しいピアノの更新について利用団体からの要望や、必要性も理解している。緊急度や必要性を考慮し、計画的に予算が確保できるよう進める。クラウドファンディングについては、可能性について検討する。
ここまで、長々と読んで頂きありがとうこざいました。
実現できるまで、粘り強く頑張ってまいります!