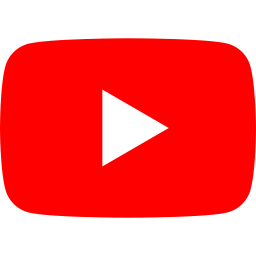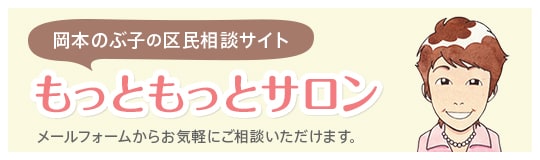決算特別委員会(総括質疑)(9/30)
令和7年決算特別委員会 初日(総括質疑)に、公明党世田谷区議団より河村みどり委員と岡本のぶ子の2名で登壇させて頂きました。
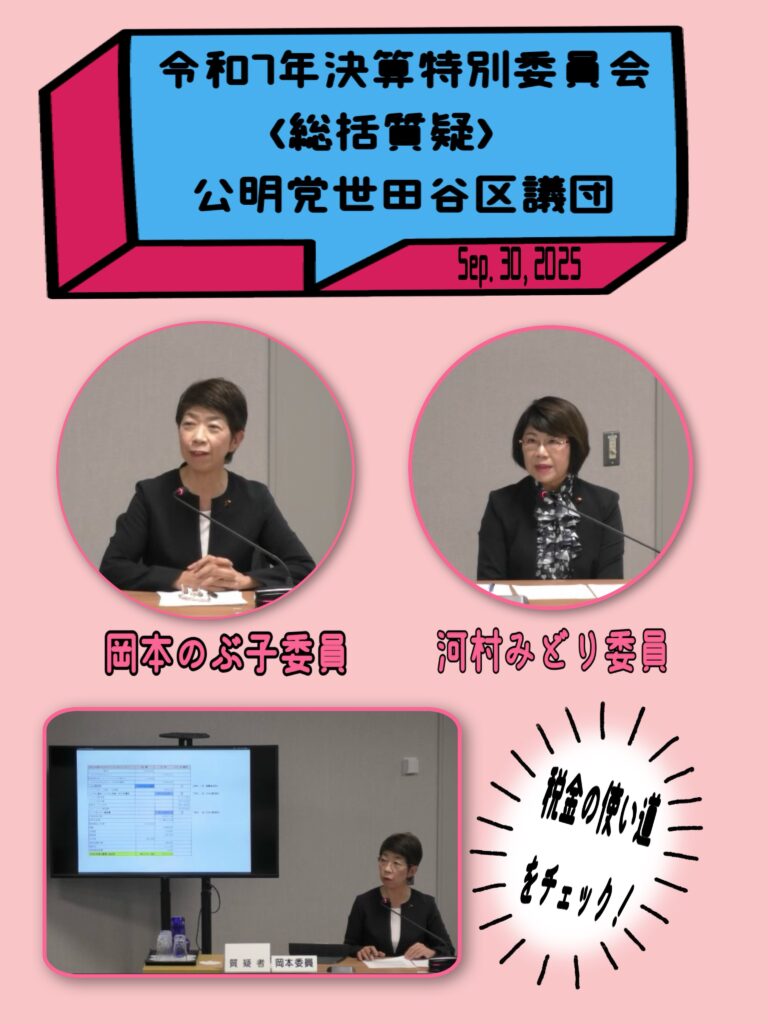

質疑の概要は下記の通りです。
1。区立小中学校における多分化学習の推進について
第3回定例会本会議で岡本のぶ子が一般質問に取り上げた「多分化学習の推進について」は、グローバル化する国際社会の中で生きる子どもたちにとって重要であり、総合的な学習や社会科などで、全児童・生徒が学習できる機会の創出を求めたものです。
その根拠として、区立小中学校の国際教育のあり方(案)に拡充が図られるとは言え、国際理解教育の体験活動に参加できる児童生徒数は年間328人。49,218人(2025年度)の全児童生徒数と比べても一部の子どもたちに限られている課題があることから質問しました。
その際、答弁は、教育委員会の部長答弁のみでした。そこで、多分化学習には、区内17大学に在籍する留学生や、在住外国人の方々のご協力を頂く提案でもあったため、区長部局の生活文化部にも関わりがあることから、再質問で保坂区長の考えを確認しました。
区長より「教育委員会と連携し、そのシステム構築を進めて行きたい。」との前向きなサプライズ答弁をいただきました。何がサプライズかと言うと、実は、再質問に対する答弁は、事前に教育委員会から頂いていたのですが、その末尾は「システム構築を模索して参ります」と一歩トーンダウンした表現でした。このサプライズ発言は、区長のアドリブ。しかし、区長の答弁は重たいものですので、事前に関係所管で調整されていた内容ではなかったとは言え、一時的な発言で終わらせない為に、区長が出席されている総括質疑で、関係する生活文化部長と教育長から答弁を頂くことにしました。
<生活文化部長からの答弁>
国際交流センターであるクロッシングせたがやでは、スペースが手狭で、拠点として事業の拡充がっ難しいという課題があるが、令和9年度には移転によりスペースが広がる予定でございます。
区ではこの機をのがさず、外国人の方からの相談の充実や地域活動への参加に向け、留学生を含め、ボランティアを希望される方を登録するなど、一層の多分化共生プランの推進を図ってまいりますので、お話の学校現場においても外国人等が活躍できるよう、その仕組みを検討してまいります。
<教育長からの答弁>
議員ご指摘のとおり、国際理解教育における体験活動に参加できる人数は限られており、より多くの児童・生徒が体験できる機会の創出が必要であると認識しております。
今後、各学校の授業での体験的な多分化学習を推進する、区内大学に在籍する留学生等による事業協力など、生活文化政策部と連携して積極的に検討してまいります。
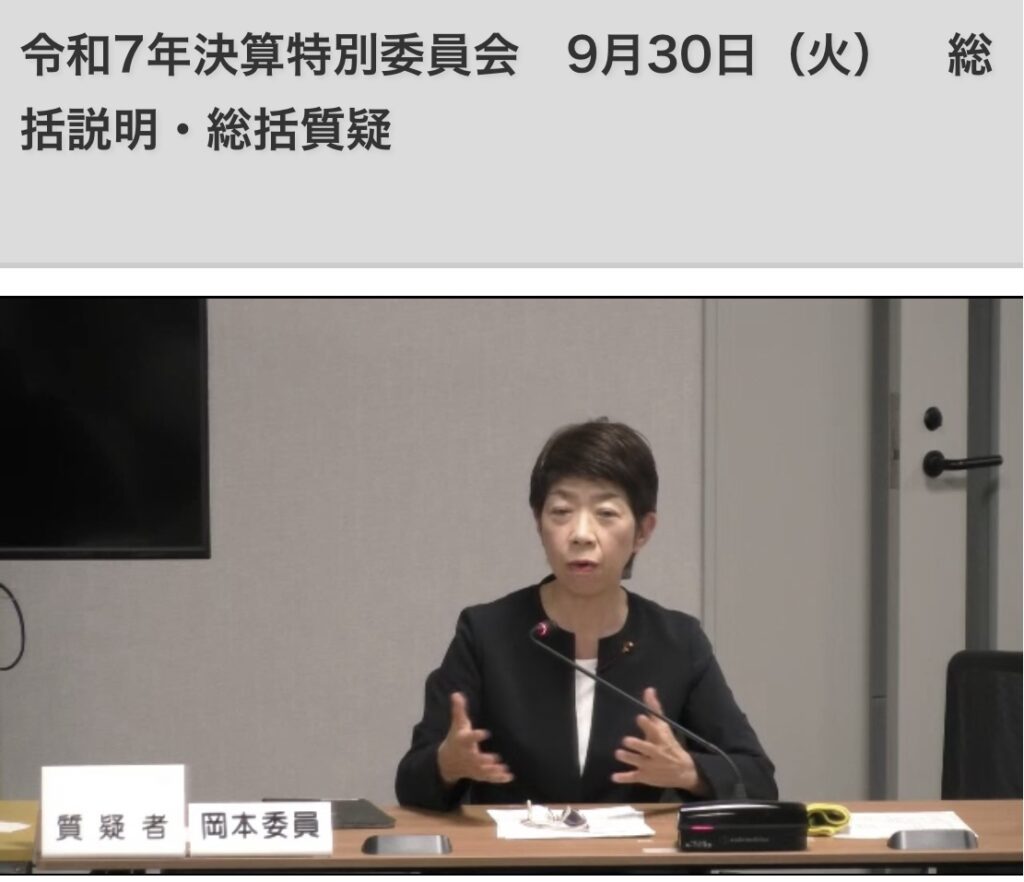
(2)区内産業の活性化に向けて、質疑を交わし前向きな答弁を頂きました。
2。区内事業者のDXの推進について
第3回区議会定例会本会議の会派の代表質問で取り上げましたが、答弁が判然としなかった為、
改めて、8月の佐賀県スマート化センター視察がきっかけとなり、HOME/WORK VILLEGEに
区内中小企業へのDX推進の仕組みの構築を求めました。
<経済産業部長 答弁>
区内には、DXの理解が浸透していない事業者が少なからずあると認識しており、事務や事業のデジタル化により経営改善に大きな効果をもたらす可能性があるため、今後は、国にガイダンスや佐賀県の事例を参考に、拠点における事業者のDX化支援の仕組みの構築を検討してまいります。
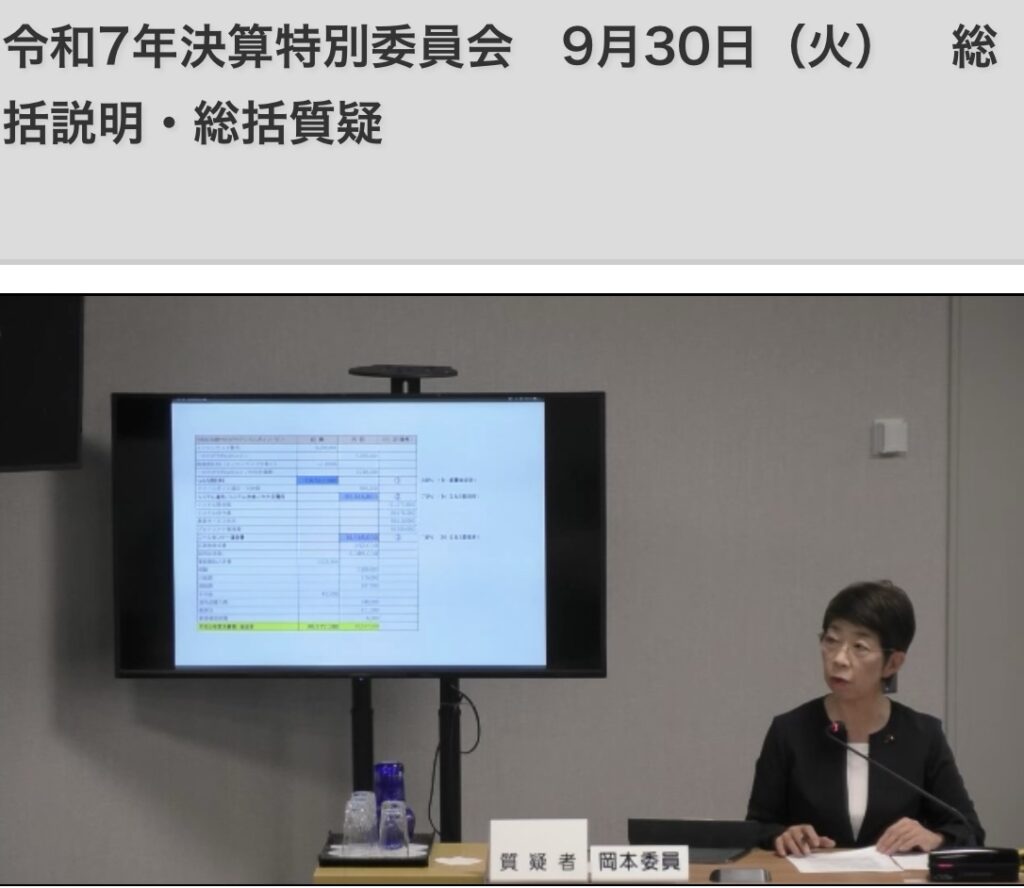
⒊税金の使い道の観点からのデジタルポイントラリー事業について
①令和6年度予算で健康福祉の重点項目に掲げられていたにも関わらず
令和6年度決算では実施計画事業に掲載されず、税金の使い道が見えない。何故か?
答弁:本事業については、試行の評価を受け、次年度以降の実施の可否を決定する予定であったこと、東京都の補助が3年間の時限的なものであることから、実施計画に位置付けなかった。
②令和5、6年度の2年間で約1億円もの税金を使って高齢者の介護予防、外出促進に使うと言いながら、その実施状況が追えない。区民への説明責任を果たす観点から、決算書の作成を改善すべき。
答弁:社会状況の変化が激しい昨今、状況に応じて計画を柔軟に見直すことも必要と考えている。今後、基本計画の中間見直しや後期実施計画の策定に着手する中で検討していく。
4.スマートウォッチを活用する東京都の「アプリを活用した高齢者の健康づくり推進事業」について
①データ活用を進めるにあたり参加者の本事業に対するご理解とデータ活用におけるプライバシー保護と安全性の担保が大切。今後、区としてデータ活用に関してどのように関与するのか。
答弁:協定を遵守するほか、事業に興味を持って頂いた方が安心して事業に参加していただけるよう対応していく。
5.令和6年度の新規事業「各総合支所・まちづくりセンターの地区・地域課題への取り組み」について
①本事業の目的に合致するよう28地区のまちづくりセンターの取り組みの情報共有を図り、区民に寄り添う地域・地区課題の解決に繋げよ。
答弁:地区アセスメントや地区展開報告会の発表内容は区のホームページに掲載し各地区の事業の見える化を図っている。今後、地区・地域課題対応予算の実績についても各地域・地区間で共有でき量取り組んでいく。
長々とここまで読んで、頂きありがとうございました。
しっかり実現するまで頑張ります!